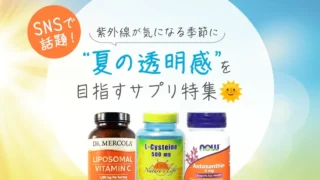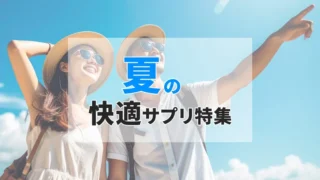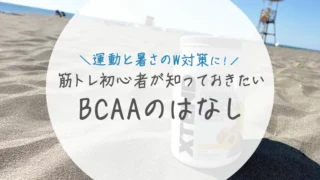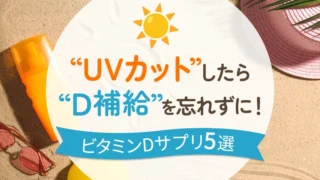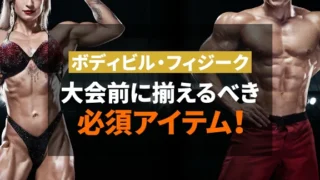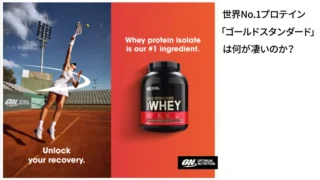Articles by Xtend&Cellucor
多くのジム通いの人が抱くよくある質問は、「筋肉の成長を最大限にするには、どれくらいのエクササイズをすればいいのでしょうか?」です。筋肉の成長を最大限にするには努力が必要ですが、やりすぎるとオーバートレーニングに陥る可能性があります。1週間あたりに行うべきセット数を適切に把握することで、目標達成への道筋を正しい方向に進めることができます。
筋肉量を増やす方法
肥大(筋肉の成長)に寄与すると考えられる要因は 3 つあります。
- 機械的張力
- 代謝ストレス、そして
- 筋肉の分解[1]
機械的張力は、力の発揮と筋肉の伸張の組み合わせから生じます。[1] 代謝ストレスは、運動による代謝物の蓄積から生じます。[1] そして、筋肉の分解は、運動によって筋肉に生じる局所的な損傷を指します。[1] さまざまなスタイルの抵抗トレーニングでは、これらの要因の 1 つに重点を置くことを選択する場合があります。
パワーリフターは高重量の挙上に重点を置いており、筋肉に大きな機械的緊張を与えます。一方、ボディビルダーは中重量の挙上を比較的高い回数で行うことが多く、筋肉に大きな代謝ストレスを与えます。
研究によると、高反復トレーニングと低反復トレーニングの両方が筋肉量の増加に効果的であることが示されています。[2] 6~20回以上の広範囲の反復を調べた研究を見ると、他のすべての変数が同じである場合、限界(または限界に近い)に達するまで行われたセット数は、筋肥大を目的とした個人のトレーニング量の良い指標です。[3]
ヒント: 筋肉量を増やすには、高反復トレーニングと低反復トレーニングの両方を効果的に使用できます。
ただし、トレーニング セットのほとんどを限界まで (または限界に近いまで) 行うようにしてください。

1回のトレーニングでどれくらいのエクササイズを行うべきですか?
一般的に、研究ではトレーニング量に対する筋肥大の反応は用量依存的に段階的であることが示されています。[4] つまり、より多くのトレーニングを行うほど、より多くの結果が得られるということです。
あるメタアナリシスでは、筋肉の成長を最大化するために、研究者らは筋肉群ごとに少なくとも週10セットのトレーニングを推奨しました。[5] 別のメタアナリシスでは、プログラムを週のセット数によって、低ボリューム(筋肉ごとに週5セット以下)、中ボリューム(筋肉ごとに週5~9セット)、高ボリューム(筋肉ごとに週10セット以上)に分類しました。研究者らは、筋肉の成長を最大化する目的では、中ボリュームおよび高ボリュームのプログラムの方が低ボリュームのプログラムよりも有利であることを発見しました。[6]
ある研究では、研究者らはさまざまな超高ボリュームのトレーニングプログラムが筋肉の成長に及ぼす影響を比較しました。彼らは、被験者を筋肉ごとに週16セットのグループ、24セットのグループ、32セットのグループに分けました。研究者らは、32セットのグループの方が16セットのグループよりも筋肉の厚さの増加が大きいことを指摘しました。[7]多くの人にとって、これほどのトレーニング量のプログラムは、時間と回復の要求のせいで難しすぎるかもしれませんが、量が筋肥大に与える影響を浮き彫りにしています。
ヒント: 筋肉量を最大化するには、毎週、筋肉グループごとに比較的高いボリュームの運動セットを使用します(筋肉ごとに約10セット以上)。
どのくらいの頻度でリフティングをすればいいですか?
最近のメタアナリシスでは、トレーニング頻度が筋肥大に与える影響が検証されました。研究者らは、トレーニング量を一定にした場合、トレーニング頻度は筋肥大に有意な影響を与えないことを明らかにしました。研究者らは、各筋肉群の週ごとのトレーニング頻度は、個人の好みに合わせて選択できると結論付けました。[8]
ヒント: スケジュールに合わせて、毎週のトレーニング量の目標を達成できるトレーニング頻度を選択してください。

ワークアウトの分割の種類
自分のスケジュールに合った週ごとのトレーニング頻度を決めたら、毎週各筋肉群を最低10セットこなせるようにトレーニングの分割方法を決めましょう。1週間に10セットを分割する方法は様々で、1つの筋肉群を1日で10セット全てこなすことも、複数の日に分けることもできます。
全身ワークアウト スプリット
全身トレーニングでは、上半身と下半身のターゲットとなる筋肉を、同じワークアウトで分割して鍛えます。このタイプのワークアウトでは、デッドリフトやオーバーヘッドプレスなど、複数の筋肉群を同時に鍛える複合運動に重点が置かれることが多いです。全身トレーニングプログラムでは、他の分割プログラムに比べて週あたりのトレーニング日数が少ないにもかかわらず、同じ筋肉を週複数回トレーニングすることが一般的です。
全身トレーニングプログラムの例
- ワークアウト1:3セット×8~12回 – ボックススクワット、ウェイトプルアップ、ディップス、ルーマニアンデッドリフト
- ワークアウト2:5セット×5回 – デッドリフト、オーバーヘッドプレス、リバースランジ、ラットプルダウン
- ワークアウト3:4セット×8回 – ダンベルフライ、ダンベルロウ、ブルガリアンスプリットスクワット、ヒップブリッジ

上半身/下半身トレーニング分割
上半身/下半身トレーニングの分割は、ワークアウトを上半身と下半身に重点を置いた日に分けます。上半身の日はベンチプレスなど、主に上半身の筋肉を使うエクササイズに重点を置き、下半身の日はランジなど、主に下半身の筋肉を使うエクササイズに取り組みます。通常、このトレーニング分割では、上半身と下半身の筋肉を週2回ずつ鍛えます。
上位/下位トレーニングプログラムの例
- ワークアウト1:上半身 – 3セット×12回 – ダンベルインクラインプレス、片腕ダンベルロウ、ケーブルフライ、ケーブルラテラルレイズ
- ワークアウト2:下半身 – 3セット×12回 – ボックススクワット、ライイングレッグカール、ランジ、カーフレイズ
- ワークアウト3:上半身 – 4セット×8回 – 懸垂、ディップス、ショルダープレス、Tバーロー
- ワークアウト4:下半身 – 4セット×8回 – ルーマニアンデッドリフト、ゴブレットスクワット、ブルガリアンスプリットスクワット
プッシュ/プルワークアウトスプリット
プッシュ/プルトレーニングのスプリットトレーニングでは、ワークアウトをプッシュ動作に重点を置く日とプル動作に重点を置く日に分けます。プッシュ動作の代表的なものとしては、腕立て伏せ、ディップス、スクワットなどが挙げられます。プル動作の代表的なものとしては、バーベルロー、懸垂、レッグカールなどが挙げられます。プッシュ/プルトレーニングのスプリットトレーニングでは、通常、1つの筋肉を少なくとも週2回鍛えます。
プッシュ/プルトレーニングプログラムの例
- ワークアウト1:プッシュワークアウト – 4セット×8回 – バーベルベンチプレス、ダンベルショルダープレス、バーベルバックスクワット、シーテッドレッグエクステンション
- ワークアウト2:プルワークアウト – 4セット×8回 – バーベルデッドリフト、Tバーロー、ラットプルダウン、シーテッドレッグカール
- ワークアウト3:プッシュワークアウト – 3セット×12回 – ディップス、インクラインベンチプレス、ボックススクワット、ハックスクワット
- トレーニング4:プルワークアウト – 3セット×12回 – ルーマニアンデッドリフト、ライイングレッグカール、プルアップ、バーベルロー

部位別トレーニング分割
部位別トレーニングのスプリットは、ワークアウトを各部位に特化した日に分けます。例えば「脚の日」では、ワークアウトのすべてのエクササイズが脚の筋肉をターゲットにします。通常、部位別スプリットプログラムでは、1つの筋肉群を週1回トレーニングします。筋肉群が非常に多いため、この種のプログラムでは、他のプログラムよりも週に多くの日数をジムに通う必要があります。
ボディパーツ分割プログラムの例
- 1日目:胸 – 3セット×12回 – ダンベルベンチプレス、ケーブルチェストフライ、ディップス
- 2日目:背中 – 3セット×12回 – バーベルロー、ラットプルダウン、メドウズロー
- 3日目:脚 – 3セット×12回 – ランジ、ライイングレッグカール、ハックスクワット
- 4日目:肩 – 3セット×12回 – バーベルオーバーヘッドプレス、ダンベルラテラルレイズ、ケーブルフェイスプル
- 5日目:腕 – 3セット×12回 – ダンベルバイセップスカール、ケーブルトライセップスプッシュダウン、ダンベルハンマーカール

ボディビルディングのプロから学ぶ
研究者たちは、全米フィジーク委員会の大会で優勝した選手を含むボディビルダーのトレーニングプログラムを分析しました。その結果、多くのボディビルダーが、1日に2つの筋肉に重点を置いたスプリットトレーニングプログラムを週5~6回実施しているというパターンが観察されました。トレーニングは、1つのエクササイズにつき6~15回の反復を2~6セット行い、一部のボディビルダーは1つの部位につき合計12~20セット行っていたと報告しています。[9]
高度なバルキングスタック
筋肉の成長を最大限に高めるには、週に何セット行う必要があるかがわかったので、次はサディクのアドバンスドバルキングスタックで、トレーニング効果を次のレベルへと引き上げましょう。このスタックで、トレーニング強度を新たなレベルに引き上げましょう。パンプアップ、持久力、そして成果がさらに向上します。
参考文献
[1] https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2010/10000/The_Mechanisms_of_Muscle_Hypertrophy_and_Their.40.aspx
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28834797/
[3] https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2021/03000/Total_Number_of_Sets_as_a_Training_Volume.39.aspx
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6303131/
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433992/
[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684266/
[7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31868813/
[8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30558493/
[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7698840/